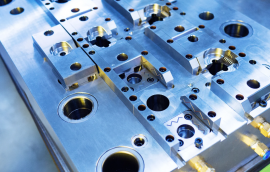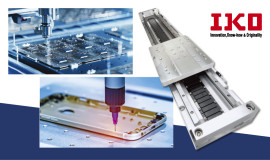Electric Vehicle(エレクトリック・ビークル)。充電式電池(バッテリー)を搭載し、蓄電された電気を使用してモーターを駆動させ走行する四輪車。今、この電気自動車の登録台数がバンコク首都圏を含むタイ全土で急増し、街中で頻繁に見かけるようになっているのを意識したことがあるだろうか。日本車?アメリカ車? いえいえ、増えているのはもっぱら中国車。それも、名の知れたBYD(比亜迪汽車)に止まらず、Deepal、AION、NETAなどといった初めて耳にするようなブランド車も増えている。その数、実に20近くもあるのだから驚きだ。一体いつからこうなったのか。そして今後の展開は。タイ自動車市場におけるEVの最新動向をお伝えする。

10数年ぶりの低成長に終わったタイの2024年自動車市場の中で、比較的堅調に推移したのがEV(7人乗り以下の小型車に限る。以下同)だ。タイ運輸省陸運局によると、昨年一年間で新車登録された全自動車はタイ全域で48万6963台。対前年比22.8%減の大幅な減少だった。市場そのものが縮小しているためEVも影響を受けたが、減少幅は10.2ポイントにとどまり、25年は早くも回復傾向を迎えている。
今年1~2月のEV新車登録台数は1万7382台。対前年同期比で3.2%増加した。自動車全体が同16.6%減と低迷し続ける中、全登録台数に占めるEVの割合は18.6%を記録。新しく選ばれる車の今や5台に1台がEVであるという実態が浮き彫りとなった。1月だけに限ってみれば新車の4台に1台近くがEVだった。
市場を牽引しているのが中国EVだ。1~2月の2か月間で最も登録台数が多かったのはBYDの5477台。EV全体に占める割合は31.5%。3人に1人がBYDを選んだ。2位は長安汽車で2041台(シェア11.7%)。人気急上昇中のDeepalとCHANGANの2つのブランドが引き上げた。3位は広州汽車のAIONで1889台(同10.9%)。中国製EVは上位20ブランド中13を占め、そのシェア合計は圧巻の91.2%に及んだ。
一方、中国勢以外で健闘したのは8位のスウェーデン・ボルボの454台(同2.6%)、11位の米テスラの318台(同1.8%)などわずか。日本勢はホンダの19位、53台(同0.3%)が最高位だった。
タイのEV市場で中国メーカーが快進撃を続けているのには、大きく二つの理由がある。一つ目が東南アジア諸国連合(ASEAN)と中国間で締結された自由貿易協定(FTA)の存在だ。通常なら80%もかかる関税が無税は大きい。ほかにも手厚い優遇策もあって、中国企業がタイ進出を強める下地はもともと存在していた。
もう一つが22年2月のタイ閣議決定「EV3.0」を受けて始まった政府の補助金支給策だ。購入1台当たり最大15万バーツを助成。これにより、EVは値段が高いというイメージの払拭がタイ国内で一気に進んだ。日本製EVなどが1台当たり100数十万~300数十万バーツと高止まりする中、50~70万バーツで購入できる中国EVは消費者に魅力的に映った。
ただ課題も残っている。補助金の支給を受けるには条件があって、EVをタイに輸入販売した外国企業には24年以降、輸入台数と同じ数のEVをタイ国内で生産するよう義務付けた。24年中に達成できなかった場合には、25年のノルマが1.5倍に膨れ上がるという懲罰的な条項もあった。
24年以降に始まったEV3.5でもこの原則は引き継がれ、懲罰条項は3倍にまで引き上げられた。条件を嫌って申請しない海外メーカーも少なからずあったが、中国企業はリスクを負ってでもタイに進出する道を選んだ。この選択が吉と出るか凶と出るかは間もなく明らかとなる。(つづく)