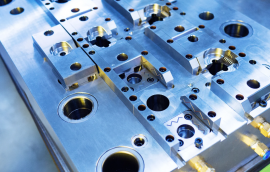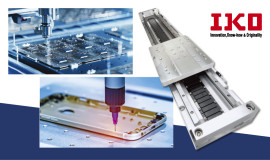ラオスのソンサイ首相が2月20日、タイの首都バンコクを訪れ、ペートンタン首相と会談。2025年が両国の国交樹立75周年であることを踏まえ、関係の強化と貿易拡大などで合意した。この中で真っ先に話題となったのが開通から丸3年が経過し、累積輸送量5000万トンを超えるまでとなった中老鉄路を活用した国際貿易だ。中国からはラオスを経てタイやベトナム、シンガポールへ、ラオスからは中国を経て欧州などに向けた新たな交易路がそれぞれ開設されるまでとなっている。また、両国政府は中老鉄路とタイ中高速鉄道を結ぶ東北部ノーンカーイ県でのメコン川鉄道橋の新設でも合意を改めて確認。貿易の活性化とともに相互の観光客誘致も拡大させたい考えだ。

中老鉄路の開通によって、ラオス政府が進めたい施策の一つに古都ルアンパバーンへの観光客誘致がある。首都ビエンチャンからつづら折りの山道を縫うように走行して350キロ超。丸一日がかりの距離にあったのが当地だった。ビエンチャンのワットタイ国際空港からルアンパバーン空港を結ぶ空路もあるが、2200メートルしかない古都の滑走路は周囲を険しい山々が取り囲んでいることから着陸が難しく、運賃が高額なこともあって庶民の足にはなりにくい。直通運行が可能な高速鉄道の開通はその意味でも長年の悲願であった。
かつてはラーンサーン王国(1353~1779年)やルアンパバーン王国(1707~1949年)が栄えたこの地方。華麗な仏教文化が根付いていることでも知られ、旧市街地全体がユネスコの世界遺産に登録されている。ビエンチャンからメコン川を約400キロも遡った上流の谷間の街。川沿いの旧市街で行われる僧侶による早朝の托鉢は、海外の旅行雑誌から「世界一の托鉢」として紹介されているほどだ。
記者(筆者)がルアンパバーンに向かったのは24年4月上旬。前日に投宿したバンビエンから中老鉄路の「快速C92号」の切符を買って乗車した。二等座席は一人16万2000キープ(約1100円)。車内はラオス人客らでほぼ満席だった。片側2列と3列の非回転席。乗車してしばらくすると、ラオス人の売り子による品数豊富な車内販売も始まった。かつての日本で乗車した新幹線こだま号、ひかり号に似た光景に懐かしさを感じた。
中老鉄路のバンビエンからルアンパバーンまで約115キロ。わずか52分の道のりだ。途中の旅客乗降駅としてビエンチャン県カーシー郡にあるカーシー駅が一駅だけあるが、停車するのは各駅停車が1日あたり上下1本のみ。通勤通学にさえ利用できず、下車する場合は当地での宿泊を覚悟しなければならない。中老鉄路にはこんな旅客駅がもう2つほどある。
ルアンパバーン駅舎は、発着駅ビエンチャン駅にも似た巨大で荘厳な造り。首都と同様に駅舎の高さは20メートル、全長も300メートルを優に超える。後に駅員に確認して分かったのだが、空の玄関口ルアンパバーン空港のデザインを一部採り入れているとか。古都のイメージとしての一体性を図りながらも、中老鉄路駅としての一貫性も合わせた建築物となっているのだという。
古都ルアンパバーンへの観光客誘致強化のためにも、ラオス政府がタイ政府と協力して進めているのが、新たにメコン川に架ける鉄道専用のメコン橋(仮称)の建設だ。タイ国鉄東北部本線のノーンカーイ線を北伸させカムサワート(ビエンチャン)を結んだタイ・ラオス架橋線の鉄道道路併設橋も存在するが、軌道が1000ミリ(メートル軌)と狭く、中老鉄路の乗り入れができないことから新設することで合意がされている。
現在の構想では25年9月までに環境影響調査を終え、26年第3四半期(7~9月)に着工。29年に完成させる計画でいる。建設予定地点は、タイ・ラオス架橋線の鉄道橋下流約30メートルの地点。ここに、中老鉄路の乗り入れを想定した標準軌(1435ミリ)の2軌道と、タイ国鉄在来線の使用を前提したメートル軌の2軌道を敷設する計画でいる。タイ側は完成した際には、タイ・ラオス架橋線を運行する全線について新たな鉄道橋を走行させる用意だ。
こうした計画の進捗もあって、中老鉄路を使った貨物輸送は好調・増加の一途だ。今年1月上旬には、ラオス・中国間の貨物輸送量が21年12月の開業からの累計で5000万トンを突破。その2カ月後には早くも5500万トンに迫ろうとしている。24年10月にはラオスから中国への生鮮品の冷蔵輸送も開始され、3000品目を超える物資の輸送が始まっている。中国人に人気の果物ドリアンのラオスでの栽培も本格化している。
旅客も堅調で、開業から3月上旬までの累積乗客数は約4900万人。このところ、3カ月毎に500~600万人の割合で増加している。1日あたりの乗客数は2万~10万人。春節や連休などまとまった休日をラオスやタイで過ごす中国人客、ラオス国内を旅行するラオス人やタイ人客が増えているという。タイ政府によるラオス人留学生の受け入れと奨学金の支給なども計画されており、鉄道・鉄道橋の建設を契機としたハード・ソフト両面での結びつきが強まろうとしている。(つづく)